UCバークレー合格:生物学メジャーの挑戦
HISTORY
中学・高校
中高一貫校に進学。テニス部で活動中に高1で大怪我。コロナも重なり試練の時期に。
進路の転機
九大オープンクラスで海洋学に魅了され、海外進学を決意。家族の後押しも大きな力に。
渡米(DVC)1学期
Geology/Calc1 など18ユニットを履修しオールA。オフィスアワー活用で学習法を確立。
DVC 2学期
Physics・Calc2・Geography・Humanitiesに挑戦するも失速。人との交流が減り成績低迷(D連発)。
夏学期
背水の陣。毎日深夜まで課題に取り組み、限界を超えてやり切る。
編入準備(秋)
UCエッセイを徹底推敲。バークレー生・メンター・家族・友人の支えで完成度を高める。
出願・結果
UCI/UCSC/UCSB/UCLA/UC Berkeley に出願。努力が実り、UC Berkeley 合格。
現在(UC Berkeley)
地球科学を軸に学修継続。高い難易度の環境で「泥臭く続ければ叶う」を実感。
INTERVIEW
学生時代と挫折の時間
Daikiさんは九州出身。中高一貫の「自称進学校」に通い、多くの生徒が「九州大学進学こそ正義」という空気のなかで学んできました。
部活動はテニス部に所属。人数の多い部で切磋琢磨していましたが、高校1年生のときに怪我をしてしまい、その後は何をするにも気力が湧かない時期が続きました。さらに、同時期にコロナ禍が重なり、人と積極的に関わることも少なくなってしまったと振り返ります。
それでも仲の良い友達とは交流を続け、自分のペースで学生生活を送っていました。

留学を決意した背景
留学を意識し始めたのは中学校時代にさかのぼります。国際連合に強い関心を持ち、自分で調べるほど国際社会への憧れが強かったのです。
「両親や祖父母も反対ではなく、むしろ『行ってこい!』と背中を押してくれました」。
お父様も若い頃にボリビアで暮らそうとしていたなど、行動力はDNAとして受け継がれていると感じています。
「ずっと日本にいると飽きちゃうな」という思いもあり、日本の大学で理系として地理を学べる場所が限られていたことも、海外へと目を向けるきっかけになりました。
学問の選択肢とアメリカの可能性
地質や地形の成り立ちに興味があり、高校1年生のころは日本の大学受験を意識して勉強に励みました。しかし「壁が高い」と感じ、徐々に海外の選択肢を現実的に考えるようになります。
しかし、Daikiさんは海洋学を志すようになりました。
そのきっかけは、九州大学のオープンクラスでの体験でした。教授たちの研究紹介のなかで、特に「マグロを使って暖流を研究する」という話に強く惹かれたのです。
「海洋学を学ぼう」と決意し、最終的にアメリカを選んだのも、多様な人々との交流や研究環境が面白いと思えたからでした。
アメリカは学問分野の幅が広く、自分の興味を伸ばせる環境があると知り、UCバークレー進学を目標に設定。そのための第一歩として、Diablo Valley College(DVC) へ進学を決めました。
アメリカ生活でのカルチャーショック
渡米してまず直面したのは、日常生活に潜む小さなカルチャーショックでした。
「ユニットバスに適応できなかったり、水が硬くてお腹を壊したり…。Safewayのスーパーでは銃を持ったセキュリティがいて、『アメリカって治安悪いんだ』と実感しました」。
また、車社会の不便さにも苦しみました。車がなければ生活が成り立たず、移動手段として頼った電動キックボードは3回も盗まれたとか。「毎回Black Fridayで買い直していました」と苦笑します。
食文化にも驚きがありました。食べ物を大量に取り、大量に残すスタイルには戸惑いましたが、「In-n-outバーガーを初めて食べたときは衝撃でした。とにかく美味しかった! 帽子まで買いました」と嬉しそうに話します。
一方で、「トイレや電車(Bart)が汚い。電車内で突然踊り出す人もいて、本当に文化の違いを感じました」と振り返ります。
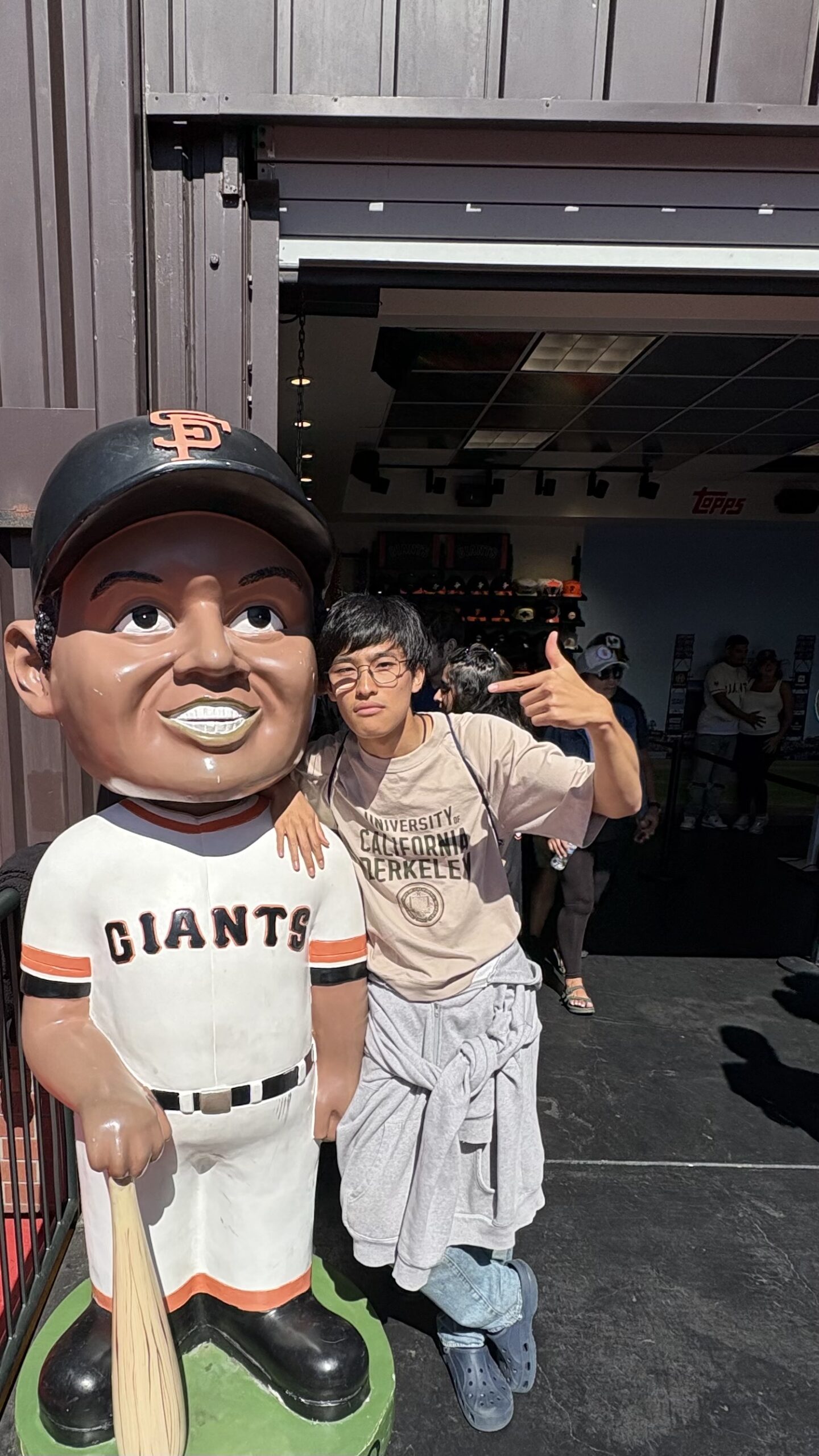
DVCでの学びと挑戦 ― 1年目
DVCでの1学期目は18ユニットを履修。
Geology、Geo Lab、Calculus 1、Counseling、Tennis、English と幅広く取り、見事にすべてオールAを獲得しました。
その裏には、徹底した行動力があります。特にGeologyの教授(韓国出身でUC Davisで恐竜研究をしていた人物)とは、Office Hourに頻繁に通うほど密に関わりました。
「テストで間違えた問題に⭕️をつけてもらって満点にしてもらったり、『これわかってるでしょ』と評価してくれたり。何度も質問して仲を深めたことで、点数を大きく伸ばせました」。
そこから得た教訓はシンプルです。
「Office Hourはとにかく大事。質問を自分からすること。そして、共通の話題があれば自然に会話が生まれる」。
さらに、Counselingの授業では「アメリカで留学生としてどう生活するか」を学び、編入情報も得られました。
その授業を担当したカウンセラーには、その後も定期的に授業の履修やmajor requirementの確認、アメリカで心地よく生活するためのヒントを教えてもらいました。
出願時期には、 月に一度 毎月Essayを見てもらう機会もあり、出願期に向けて大きな支えになったと言います。
Tennisの授業では仲間を作るきっかけが増え、スポーツの力で友達関係が広がっていきました。「スポーツのクラスは友達づくりにおすすめです。コミュ力に自信がなくても、自然と人と関われます」。
この時期には Japanese Association(JA)のMedia Officer として活動し、Instagram投稿やBBQイベントのポスター作成なども担当。
「自分のチャンスを活かして、いろんなことに挑戦しました。人間関係のバランスが取れていて、すごく充実したセメスターでした」と話します。
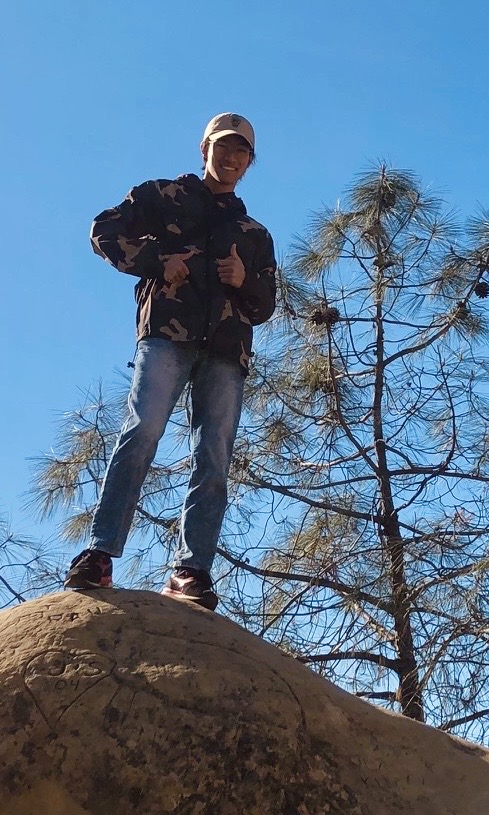
DVCでの学びと苦難 ― 2年目
2学期目は、Physics、Calculus 2、Geography、Humanities の計15.5ユニットを履修しました。
しかし、ここから苦しい時期が始まります。
Physicsの教授はロシア出身で、英語が聞き取りにくく、Office Hourでも満足な回答が得られませんでした。
一方、Calculus 2は「ハイブリッド授業(対面+オンライン)」を選びましたが、逆に出席しなくても大丈夫だと思って授業をサボりがちに。結果として、キャッチアップが追いつかず、Finalも失敗。
「対面授業の強制力がある方が、結局は勉強するようになる」と、そこから学びを得ました。
さらにHumanitiesのプロジェクトも後回しにしてしまい、こちらも疎かに。最終的にはPhysics以外すべてDという結果に終わってしまいました。
「人に会わなくなったのも失敗の一因でした。物理の作業量が多すぎて、遊びや息抜きをしなくなった。結果的にリフレッシュできず、集中力も落ちてしまったんです」。
この経験から「誰かと一緒に勉強することが集中力につながる。人との交流は息抜きになる」と強く学んだと振り返ります。

夏学期 ― 背水の陣
続く夏学期は、まさに背水の陣。
Mathの授業は宿題の量が膨大で、家に帰ってから朝2時まで宿題をやり続ける日々。睡眠は5〜6時間しか取れず、心身ともに追い詰められていきました。
「もう落とせない。バークレーに行けなくなっちゃう」。その一心で勉強を続け、限界に近い状態まで自分を追い込んでいました。
「宿題をやっていたら気づいたら泣いていた。躁鬱に近いくらい病んでいた」と打ち明けます。
それでも諦めず、必死に踏ん張った夏。短期集中のこの学期を乗り越えたことが、後の自信につながりました。
「始まる前はジムに通ってリフレッシュできていたけど、授業が始まってからは本当に余裕がなかった。それでも最後まで粘り切れたのは、自分でも驚きです」。
2年目秋 ― エッセイとの戦い
秋学期は授業がどれも難しく、並行して編入用エッセイの作成に取り組むという大きな挑戦が待っていました。
「エッセイと授業の両立が本当に大変で…。最終的にはエッセイを優先して、Bioをドロップしました」と振り返ります。
この時期、UC BerkeleyのアドバイザーがDVC生向けに開いたセッションにも参加。授業の違いやメジャーごとの進路を直接聞く機会があり、大きな参考になったといいます。
エッセイの基礎は、留学エージェントのYukoさんが公開していた過去の合格エッセイから学びました。さらに、実際のBerkeley生やSMPMのメンター、日本人のBerkeley卒業生、そして両親まで、多くの人にレビューをしてもらいました。
特に大きな支えになったのは、OCC(オレンジコーストカレッジ)に通う友人の存在。
「電話で一緒に悩みを話したり、Essayのレビューをし合ったり。『受かるかなー』と不安を分かち合える仲間がいたのは、本当に大きかったです」。
最終的に、11月の初めにはエッセイを書き上げ、出願のフォーム入力にも2〜3週間をかけて完成。
「エッセイで落ちることはないだろう」というところまで突き詰め、自信を持って提出することができました。

出願後の心境
出願を終えた後も、不安は完全には消えませんでした。
「受かるか落ちるか、本当に半々の気持ちでした」。
同時期に履修していたBio131やChem120は非常に難しく、学業面でのプレッシャーも大きかったといいます。
そんななかで、小学校の算数の放課後教室で子どもたちに時計の読み方を教えた経験を、UCエッセイに盛り込んだり、52Hzという学生団体で高校生向けに「コミカレからの編入」を紹介したりと、課外活動も丁寧に積み上げていました。
親の会社の手伝いでは機械の仮組み立てを行い、海洋学に関する活動にも積極的に参加。
「自分がやってきたことをすべてまとめ、課外活動欄は意地でも埋めました。嘘をつかず、素直に、論理的に伝えることを心がけました」。
UC Berkeley合格とその後
Daikiさんが出願したのは、UC Irvine、UC Santa Cruz、UC Santa Barbara、UCLA、そして第一志望のUC Berkeley。さらにUSFにも出願し、Need-basedの奨学金を狙いました。
UCエッセイは9月から書き始め、11月ギリギリまで推敲を重ねました。留学エージェントのYukoさん、DVCのCounselorのMutt Munday、両親など多くの人に見てもらい、論理的かつ素直な内容に仕上げました。
「高校時代の経験は書くなと言われていたけど、必要だと思ったからあえて書いた。嘘をつかず、正直に伝えました」。
課外活動欄は20個を埋め切り、最後まで全力で挑んだ結果、見事にUC Berkeleyに合格。夢の舞台に立つことができました。

UC Berkeleyでの学び
Berkeleyに進学後は、生活と学業の両面で大きな変化を感じました。
まず授業スタイル。DVCに比べて授業時間は短いのに内容は格段に難しく、1コマ1時間に凝縮されています。
「だからこそ勉強量は増えたし、単位数に比べて負担は重い。けれど、その分やりがいもありました」。
また、Berkeleyには一つの分野を徹底的に突き詰める学生が多く、目標意識の高さに圧倒されました。
「学生団体やアクティビティも豊富で、明確な目標を持っている人にとっては最高の環境です」。
Berkeleyの魅力の一つとして、BARTが無料になったことも挙げます。通学の利便性が増し、生活の負担が軽減されました。
残念ながら実験系の海洋学授業がなく、座学中心となりましたが、それでも「地球科学や資源に関する学びを深める」という強い軸を持ち続けました。

留学を通じての成長
UC Berkeleyでの学びを経て、Daikiさんは大きな成長を実感しました。
「泥臭く頑張っていたら、意外と物事は叶うんだなと感じました。諦めずに続けていれば必ず報われる」。
また、自分とは違う専攻で、比較的容易な課程を楽しそうに過ごしている学生を見て、人生で初めて嫉妬という感情を抱いたとも話します。
「それも含めて、人間として成長したと思います」。
一方で、Berkeleyの授業を通して「自分の英語力の不足」を痛感し、改めて英語を学び直している最中でもあります。
今後の進路と夢
本音を言えば修士課程に進みたい気持ちは強いものの、金銭的なハードルもあり迷いは残っています。
それでも将来的には、海洋資源の開発を行う団体で働くことを目指しています。
「日本はEEZが広く、資源の埋蔵量も豊富。『失われた30年』と日本が語られるけど、未来のために改善したい。地球と人間が共生できる社会をつくりたいんです」。
まずはアメリカで経験を積み、その後は日本でのキャリアに繋げたいと考えています。
留学生へのメッセージ
最後に、これから留学を目指す学生へのメッセージをもらいました。
「泥臭く頑張っていれば、なんとかなる。 どんなに打ちひしがれようが、成績が落ちようが、諦めずにやり続けること。必ず光は見えてきます」。
さらに、アメリカにはCounselingやAcademic Resourceといったサポートが整っているので、それを活用することが大切だと強調しました。
まとめ
Daikiさんのストーリーは、挫折も苦悩もすべて含めて「挑戦する姿勢の価値」を教えてくれます。
DVCでの失敗も、夏学期の壮絶な努力も、エッセイ作成での葛藤もすべてが糧となり、UC Berkeleyという舞台へと繋がりました。
「泥臭く頑張ればなんとかなる」――その言葉は、これから新しい世界に飛び込む誰かの背中を、きっと力強く押してくれるはずです。




